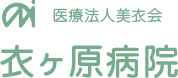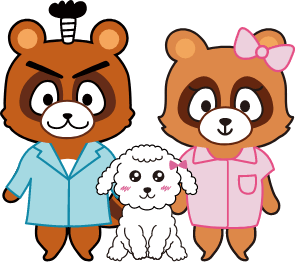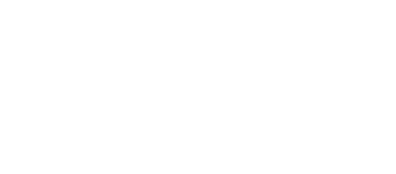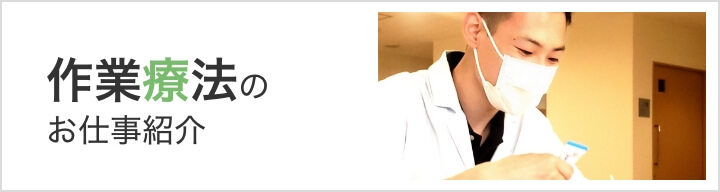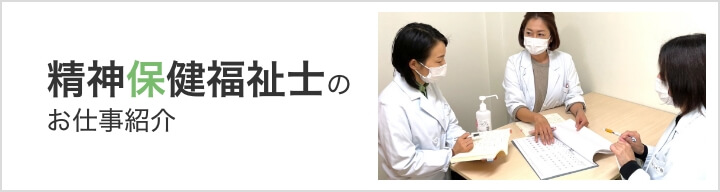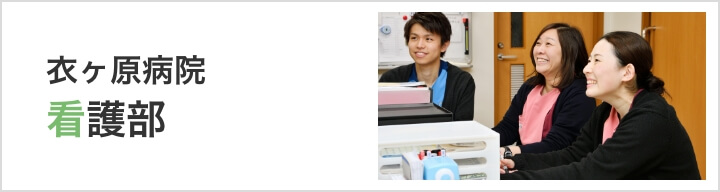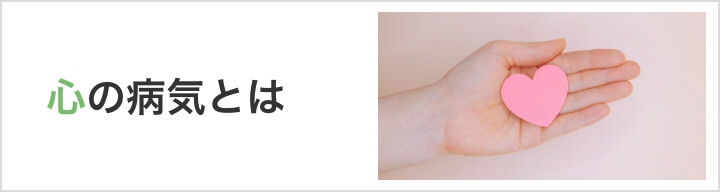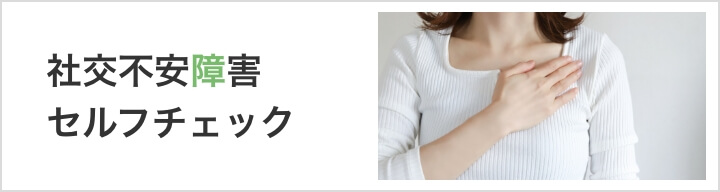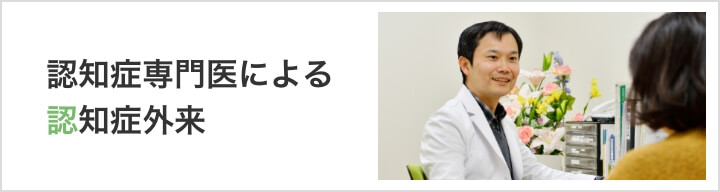2024.04.2 お役立ち情報
社交不安障害/社交不安症(SAD)(あがり症、対人恐怖)について
社交不安障害/社交不安症(SAD)は、ある特定の状況や人前で何かする時に緊張感が高まって不安や恐怖を感じ、次第にその場面を避けるようになる病気です。
若年期に発症することも多く、症状が長期にわたると日常生活にも大きな影響を及ぼします。
性格の問題と混同される場合もありますが、極度の緊張感、恐怖感、不安感などのため、人との交流を避けてしまい、症状が強くなると引きこもりがちになり、自信をなくしてうつ病を併発することもあります。
対人恐怖のある引きこもりの方にも多い症状と言えます。
目次
社交不安障害/社交不安症の症状について

1. こころにあらわれる症状
初対面の人と会う、大勢の人前で発表や挨拶をする、人前で字を書く、人前で電話をかけるなど、他人から自分に注目があつまるような状況で何か失敗して自分が恥をかくのではないかと、強い不安や恐怖、緊張を感じるようになります。
2. からだにあらわれる症状
緊張し体が震える、頭の中が真っ白になる、赤面したり発汗したりする。のどが渇く。
声がふるえてしまう。など
3. 社会生活での症状
- 会議などで人前で自分の意見を言えない
- 人前でプレゼンテーションができない
- 受付や、同僚、上司の前で字が書けない
- 人がいるときに電話をすることができない
- 家族や仕事関係の行事、会合に参加できない
対人関係に対する極度の不安や緊張とそれにともなって現れるからだの症状が、自分の発言や行動に影響し支障をきたしてしまうため、日常の社会生活に障害がでてしまうのが社交不安障害/社交不安症です。

社交不安障害/社交不安症の原因は?
SADの方は、脳の中で不安や恐怖の反応を起こす基となる脳の中の扁桃体という場所が過活動している状態と言われています。
通常はその活動を抑えるために重要なセロトニン神経の調節が行われるのですが、SADの方はセロトニンが十分放出されず、セロトニンのバランスがわるくなり扁桃体の過活動が止まらず続いてしまい、発症するといわれています。
社交不安障害の治療について
1. 内服薬について
うつ病やパニック障害等に使用される、抗うつ薬(SSRI)が主体になります。
SSRIにより偏桃体でのセロトニンのバランスが調整されて効果がはっきされます。SSRIは効果が出るまで2週間程度かかります。効果が十分に感じられるまで増量し、効果がある用量を症状が軽快するまで飲み続けていただく必要があります。
自己判断で薬の量を調節すると症状の改善が難しくなる可能性があるため、必ず医師の指示に従ってお薬の服用をすることが大事です。
2. 精神療法
精神科医師との診察において、病気についての理解やもともとの性格的なことだけが問題なのではなく、治療が必要な疾患であることを理解していただくことがとても大切になります。
SSRIなどにより症状が軽快してきたら様々な苦手な場面での成功体験を積み重ねることが大切です。
(暴露療法)成功体験の積み重ねが社交場面での自信になることでしょう。

気になる症状があればお気軽にご相談ください
当院では精神科専門医による診断治療や各種心理検査、カウンセリング等受けることが可能ですので、気になる症状があれば是非お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
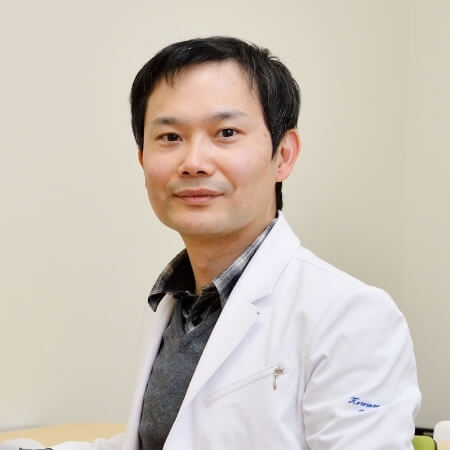
副理事長 加藤 豊文
精神科医
精神保健指定医
認定産業医、精神科専門医・指導医(日本専門医機構)
認知症診療医(日本精神神経学会)
認知症臨床専門医(日本精神科医学会)
認知症サポート医
老年精神医学会認定医
臨床研修指導医
児童思春期精神医学対策講習会スタンダードコース終了(日本精神科病院協会)
児童思春期精神医学対策講習会アドバンスコースⅠ終了(日本精神科病院協会)
産業保健アドバイザー
名古屋平成看護医療専門学校 看護学科 非常勤講師
| 専門分野等 | 精神医学一般、うつ病リワーク、認知症 |
|---|---|
| 所属学会 | 日本精神神経学会、日本心療内科学会、日本うつ病学会、日本老年精神医学会、日本アロマセラピー学会 MCT-J(メタ認知)ネットワーク会員など |
カテゴリー一覧
- 月別アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
最近の投稿
- 2026.01.17美衣会ライフ 第6回ころも感謝祭 結果発表
- 2025.12.17美衣会ライフ 第6回 ころも感謝祭
- 2025.12.10大切なお知らせ 2月25日(水)代診のお知らせ
- 2025.12.10大切なお知らせ 1月28日(水)代診のお知らせ
- 2025.11.25大切なお知らせ 1/17・1/24 加藤豊文医師の診察受付時間変更のお知らせ


その他のご案内
More Information
出版書籍のご案内
Publications
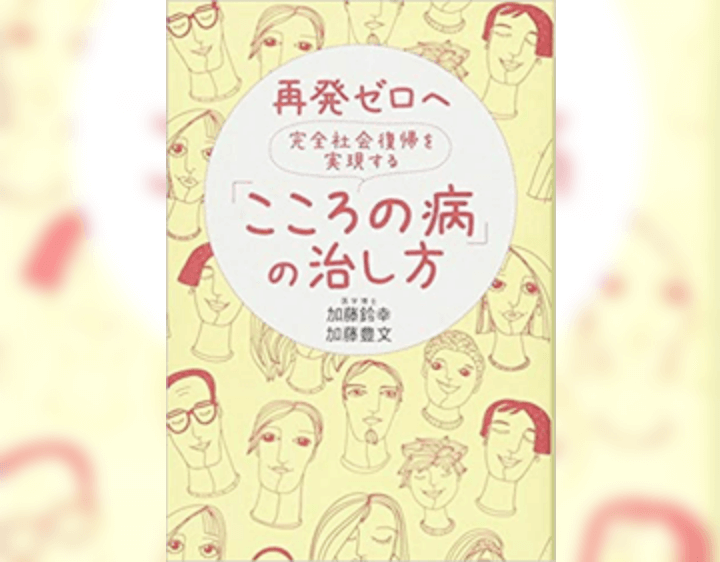
再発ゼロへ 完全社会復帰を実現する
「こころの病」の治し方
当院理事長 加藤鈴幸医師と副理事長 加藤豊文医師の著書が出版されました。
全国の書店またはAmazon等のオンライン書店でご購入いただけます。